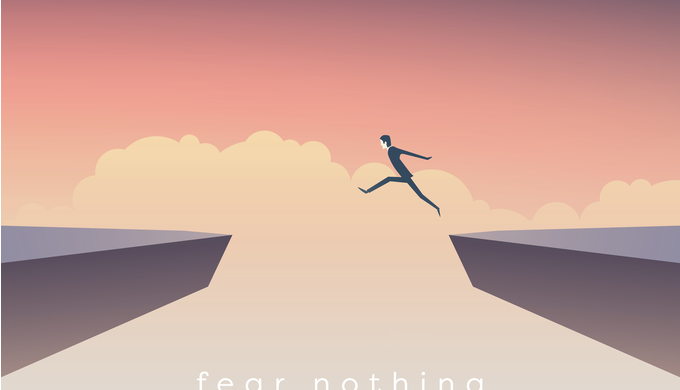※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています
弁理士は専門職ということで、結構転職が盛んな職種です。
昔は別の特許事務所に移ったり、独立開業したりということが多かったですが、最近では、特許事務所に勤務する弁理士が企業の知財部への転職する、というケースも結構見かけるようになりました。
ちなみに、日本弁理士会会員の分布状況によれば、2020年6月時点で約24.1%の弁理士が会社勤務しているそうで、今や企業の知財部門は弁理士のメインの就職先の一つ。
というわけで、この記事では、
特許事務所で弁理士やってるけど、企業の知財部に興味がある
という人に向けて、事務所から企業への転職の成功のポイントを書いてみたいと思います!
なお、私は学生時代に弁理士資格を取り、新卒で企業の知財部に入って以来10年近く企業知財の仕事をしています。
まわりで、企業→事務所、事務所→企業の転職をした人も多く、且つ私自身も企業で採用に関わったことがあるので、参考にして頂けると思います。
- マイナビエージェント
 ※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。)
※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。) - リクルートエージェント ※転職エージェントの最大手。求人案件が非常に豊富
- ビズリーチ ※ハイクラスの求人案件が多い。企業の採用担当者が閲覧しており、スカウトを受けられる
本記事の内容
弁理士の知財部への転職が成功するかは企業のニーズ次第
まず最初に結論を言ってしまうと、
特許事務所の弁理士が企業知財部への転職に成功するかは、企業側のニーズに合うかどうか次第
であると言えます。
当然ながら、企業側はなにかの目的があって採用活動します。
例えば、
- 業務拡大で特定の技術分野に強い人がほしい
- 人が辞めたので欠員を補充したい
などですね。
そういった企業側の採用目的を反映させたのが募集ポジション(求人票に記載される、業務内容や期待する役割)で、これに特許事務所で弁理士をやっている経歴が合うかがポイント。
その際、いくら弁理士資格があっても、企業側のニーズに合わなければ、ミスマッチで選考に落ちるということは十分にあります。
以下、詳しく説明します。
企業の採用担当者が考えること
まず、一般論として、企業側が採用の際に考えることを整理しておきましょう。
企業における採用の場面においては、
- 職歴がポジションと合うか?
- 待遇・年収がすり合うか?
- キャラクターが組織に合いそうか?
- 能力は高いか?(優秀そうか?)
- 今後の伸びしろがあるか?(ポテンシャル)
あたりを総合的に見て、候補者の採用の可否を判断します。
もちろん、企業や採用担当者によってどういった項目を重視するのかは変わってくるのですが、結局の所、企業の採用担当者の一番の関心事は、
候補者が自社でワークするのか?(報酬に見合う以上の役割をはたしてくれるのか?)
ということです。
候補者が特許事務所の弁理士であれば、上記の判断は、「募集ポジションに対して特許事務所での職歴が合うか?」というところが大きなポイントになるわけですね。
ここで、同じ知財業務とはいえ、特許事務所と企業知財部とでは、やってることの違いが結構あります。
一般的には、特許事務所は対特許庁への書面作成業務に特化しているのに対し、企業知財部は特許権利化や調査、係争対応など幅広く行うことが多いです。
なので、企業の募集ポジションによって、特許事務所の職歴が評価されるか否かが大きく変わります。
大手メーカー知財部が弁理士を採用する理由
例えば、私の前職である大手メーカーの知財部では、特許事務所出身の弁理士を採用するケースが結構ありました。
これはどういった意図でしょうか?
メーカーがあえて特許事務所出身の弁理士を採用するのは、特許出願や権利化の即戦力として期待されているからに他なりません。
大手メーカーの知財部では、自社内で特許明細書や意見書・補正書の作成を行うケースが結構あります。
特許事務所出身の弁理士であれば、まさにそういった仕事の経験が豊富なので、強みがダイレクトに活かされます。
つまり、企業の募集ポジションと特許事務所の経験がマッチしているわけですね。
逆に言えば、募集ポジションで明細書作成や中間処理等を求めていなければ、特許事務所の経験があまり評価されない可能性はあるかもしれません。
もちろん、弁理士として知財の法律や実務を知っているのは強みですが、他に企業知財部出身の候補者がいる場合、同じ土台で戦うことになります。
弁理士の強みを企業知財部への転職で活かすには?
上で述べたように、企業が特許事務所出身の弁理士を採用する理由としては、主に「特許出願や権利化の即戦力として期待されている」からです。
しかし、企業内でがっつり明細書や中間処理を内製するという場合を除き、特許事務所でやってきた業務と企業知財部でやる業務とではギャップが有るのが通常です。
その場合、他の候補者(例えば、企業知財の経験者)とどう差別化できるかがポイントになります。
では、特許事務所の業務を経験した弁理士は、どのような強み(経験やスキル)がアピール材料になるのでしょうか?
ポイントとしては、出願・権利化業務の経験に加えて、プラスアルファがあるかどうかだと思います。
発明発掘に深く関わった経験
上述したように、特許事務所出身の弁理士は書面作成能力を期待されて採用される場合が多いです。
このとき、書面作成能力と親和性があり、評価されやすいのが発明発掘の経験・スキルです。
例えば、
あんまり固まってない発明に対して、クライアント側の発明者にヒアリングして情報を引き出して、発明の形に仕上げた
というような経験でしょうか。
企業知財部においては、開発者から発明ヒアリングして、それをある程度まとめてから特許事務所に依頼する(あるいは社内で明細書をドラフトする)というケースが多いです。
従って、発明発掘の経験が豊富だったり発明者とうまくコミュニケーションをとれそうな人は、採用において有利になります。
明細書の質を評価できる力
明細書の質を評価できる力というのも大事です。
企業によっては、社内では明細書の作成を行わず、特許事務所に外注し、できた明細書をチェックする、というところもあります。(むしろこちらのパターンの方が多い)
このとき大事なのが、会社の立場で明細書の質を評価できるか?ということです。
会社の事業を守るために、
- クレーム文言をこうする
- こういったカテゴリを入れる
- 実施例にこういったものを書いておく
といった観点で、明細書をチェックしたり、ブラッシュアップしたりすることができれば担当者としては合格!
特許事務所で働いていた頃に、クライアントの立場に立って、どういうクレームの書き方をすればよいかをしっかり考えた、クライアントに提案した、という経験はアピール材料になるでしょう。
法律の強み
弁理士であれば、当然、法律に強いことはアピール材料になります。
企業にいる人で弁理士資格がある人は存外に少なく、法律に詳しい弁理士は重宝されます。
事務所時代に、法的にややこしい件があって、こう解決した、みたいな経験があると良いでしょう。
特許出願、権利化以外の業務経験
特許事務所において業務の比率的に少ないですが、特許調査や鑑定、無効審判などの対応の経験があれば、さらに有利です。
企業知財部では、わりと調査とか抵触判断などの業務があります。
従って、特許出願・権利化の経験に加えて、上記のような業務の経験があれば、企業受けは良いでしょう。
企業経験の無い弁理士は敬遠される可能性も?
あと、企業の採用で考慮される要素として意外と重要なのが、企業経験の有無です。
これは、知財の仕事に限らず、一般企業で働いたことがあるかどうかの話でして、例えば、
特許事務所に入る前にエンジニア等で企業に勤務していた
などの経験があれば有利に働くでしょう。
逆に、新卒から特許事務所に入ったなどで一般企業で働いた経験の無い弁理士は、企業から敬遠される可能性があります。
というのも、特許事務所は小規模の組織で、且つ基本的には事務所の中に個人商店が入っているような構成。
一方で、企業はものごとを進めるのに関連部署とやり取りしなければならなかったり、何かを進めるのに上司(場合によっては上司の上司)の承認が必要だったりと、組織のスタイルが全く異なります。
また、代理人の立場とクライアントの立場とでは、知財に対する考え方も異なります。
(事務所は案件獲得と登録査定を得ることにインセンティブがあるのに対して、企業は権利活用や費用対効果を意識しなければならない。)
そのため、企業経験が無い弁理士(特にそれなりにシニアの人)の場合、会社になじまないのではないかと思われ、採用するのをためらう可能性があります。
もし企業経験が無ければ、ポテンシャルがある若いうちに動いた方が良さそうです。
企業知財部への転職活動の進め方
ここからは、企業知財部への転職の進め方についてです。
企業知財への転職は大手転職エージェントを使うのが基本
企業への転職であれば、大手の転職エージェントを使うのが基本です。
知財部とは言え企業への転職なので、よく名前を聞くような大手の転職エージェントが知財部の求人案件を豊富に持っています。
私の転職活動の経験なども踏まえて、下記の3つをおすすめします。
- マイナビエージェント
 ※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。)
※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。) - リクルートエージェント ※転職エージェントの最大手。求人案件が非常に豊富
- ビズリーチ ※ハイクラスの求人案件が多い。企業の採用担当者が閲覧しており、スカウトを受けられる
中でも、マイナビエージェント![]() は面接対策などサポートが手厚く、20代、30代の転職に定評があります。
は面接対策などサポートが手厚く、20代、30代の転職に定評があります。
私もマイナビエージェントに紹介してもらった企業に転職を決めました。
(※マイナビのプロモーションを含みます。)
※面接対策などサポートが手厚く、特に20, 30代の方におすすめ!
※無料で登録できます
30代後半以降のシニア層であれば、ビズリーチはおすすめです。
ハイクラスの求人案件に強い転職サイトなので、マネージャークラスでの転職を希望する方は登録必須です。
※ハイクラスの求人案件が豊富!
※無料で登録できます
なお、知財の転職エージェントのおすすめについては、下記の記事で詳細を書いています。
私が転職活動した際に使った転職エージェントの感想も書いているので、ぜひ参照してください!
 知財・弁理士の転職エージェントおすすめ6選|体験談も紹介します
知財・弁理士の転職エージェントおすすめ6選|体験談も紹介します
まとめ
というわけで、特許事務所出身の弁理士が企業への転職が成功するかどうかのポイントについて書いてきました。
まとめると、
- 募集ポジションに対して特許事務所での職歴が合うかが重要
- 企業が特許事務所出身の弁理士を採用するのは、特許出願や権利化の即戦力として期待しているから
- 特許事務所の弁理士の立場で発明発掘などの経験があると、有利に働く可能性あり
- 一般企業での勤務経験がないと不利に働く場合も(特にシニア)
- 企業への転職活動は大手転職エージェントを使うのが基本
ということですね。
企業知財部への転職を検討されている方の参考になれば幸いです!
なお、弁理士の転職については下記の記事で詳細を書いています。
弁理士に限らず、知財の仕事で転職しようとしている方には参考にして頂ける内容となっていますので、ぜひご参考に!
 弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント
弁理士の転職ノウハウ総まとめ!|知っておくべき10のポイント
- マイナビエージェント
 ※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。)
※企業への面接対策などサポートが手厚い。特に20代〜30代の方におすすめ(※マイナビのプロモーションを含みます。) - リクルートエージェント ※転職エージェントの最大手。求人案件が非常に豊富
- ビズリーチ ※ハイクラスの求人案件が多い。企業の採用担当者が閲覧しており、スカウトを受けられる