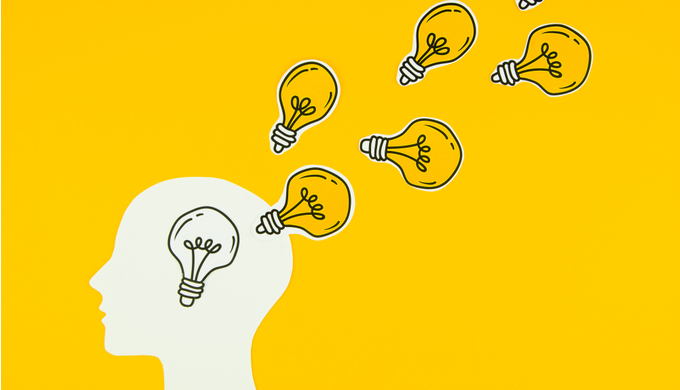弁理士は専門職であり、少々特殊な性質の業務をこなしていくことになります。
そのため、弁理士は、結構向き不向きが激しい職業の1つなんじゃないかなと思っています。
では、いったいどんな人が弁理士に向いているのか?
この記事では、弁理士に向いている人の性格を5つ挙げつつ、その性格がどのような場面に生かされるのかを解説したいと思います!
本記事の内容
弁理士に向いている人はこんな性格!
弁理士に向いている人の性格を挙げてみたいと思います。
もちろん、弁理士にも色んなタイプがおり、皆が皆同じような性格というわけではないのですが、だいたいのイメージはつかめるかなと。
ちなみに以下は特許事務所で働く特許系の弁理士を想定しています。
(特許技術者も大体同じかんじです。)
- ペーパーワーク大好き
- 聞き上手
- 勉強家
- 論理的である
- ひねくれ者?
1.ペーパーワーク大好き
まず弁理士に向いてるのは、ペーパーワークが大好きな(少なくとも苦にならない)人ですね。
というのも、弁理士は文章を書いて読んで書いて読んでをひたすらやる仕事だから。
弁理士になった暁には、文章漬けの日々が約束されています(笑)
弁理士が目を通さなければならない書類としては、具体的には、
- 特許文献
- 拒絶理由通知
- 審査基準などのお役所の書類
- 判例
- 法律書
- 条文
- 技術書や論文
なんかがあります。
そして、上のような書類を読むだけにとどまらず、明細書や意見書・補正書といった文章を書きまくらなければなりません。
というわけで、外に出て人とコミュニケーションするより、室内で黙々と書類を読んだり書いたりするのが好きな人が向いています。
2.聞き上手
意外かもしれませんが、弁理士には、話し上手な人が必ずしも向いているわけではありません。
それよりも大事なのが、聞き上手であることです。
弁理士は、技術者がした発明をヒアリングして、それをもとに特許明細書を作成します。
この時に非常に重要なのが、「発明者からいかにして発明のポイントを聞き出せるか?」です。
この発明のポイントというのがくせ者なんですよね・・・。
発明のポイントは、「従来の技術には無い新しい要素で、且つ発明の効果に寄与するもの」と言い換えることができますが、発明者がこれをズバッと語ってくれることはまずありません。
なんか新しいものを思いついたけど、従来技術との違いがよくわからない(あるいは従来技術との違いだと思っているものが実は本質的ではない)ということがほとんどです。
さらに、発明者の中には結構気難しい人もいたりして、そこをうまいことやらないと気分を害してしまったり、正確な情報が聞けなかったりします。
そんな発明者に対して、適切な質問を投げかけ、必要な情報を聞き出し、発明の本質に迫っていけるかが、弁理士としての腕の見せ所。
できる弁理士と言うのは、この聞き出す力が抜群に優れています。
発明のポイントをスムーズに引き出して、質の高い明細書を作れば、クライアントからは絶大な信頼が得られます。
3.勉強家
弁理士には勉強家が向いています。
というのも、弁理士業務に必要な知識や情報は、どんどんアップデートされていくからです。
特許法などの知財の法律は毎年のように改正されますし、新しい判例もどんどん出てきて、実務のスタンダードがいきなり変わったりします。
弁理士として一線で活躍したいのであれば、こういった情報(国内だけでなく海外も)をいち早くつかんで実務に生かさなければなりません。
そして、技術的な専門知識もキャッチアップが欠かせません。
当然ながら、技術も日々進歩していきますし、ときには今まで扱ってこなかった技術分野の明細書を書かなければならないことだってあります。
つまり、弁理士としてやっていく限りにおいては、常になにかを勉強し続けなればならないのです。
4.論理的である
知財の仕事をやる上で論理的であることは大事です。
要は、根拠に基づきながら、相手を納得させる様な議論ができるかということですね。
知財の業務では、相手(審査官、審判官、裁判官、訴訟相手等)に対して自分の主張を通さなければならない場面がしばしばあります。
その際に、相手を納得させるためには、何らかの根拠に基づいた説得力のある議論をすることが不可欠です。
「おれはこう思うんだ!」と熱く語ったところで、根拠が無いと誰も話を聞いてくれません(笑)
明細書作成にしてもそうですよね。
- この発明はこういう構成でこのような効果が得られる
- 何故ならこの構成がこういう働きをし、こうなるからである
- さらに、このことは実験によっても実証されてる。
みたいに、明細書は論理的な構成になっています。
すなわち、明細書などの特許に関する文章を書く際には、論理構成を意識する必要があるわけです。
なので、「わたしは理屈っぽいのはキライよ!」とか、「おれは感性で生きているんだ!!」みたいな人は向いてないと思います(笑)
5.ひねくれ者?
意外なところで言うと、弁理士はちょっとひねくれている性格の方が向いていると思います。
というのも、弁理士の仕事の中には、他人の主張の弱点をつく(悪く言えばあらを探す)要素が多分に含まれるからです。
例えば、弁理士の仕事のメインのひとつである拒絶理由通知応答なんていうのは、まさにそんな仕事です。
特許出願が特許庁で審査される際に、必ずと言っていいほど拒絶理由通知というものを受け取ります。
拒絶理由通知には、例えば、「あなたの発明は昔からある技術と大して変わらないから特許にできません」みたいなこと(拒絶理由)が書いてあり、これに反論して特許庁に特許を認めさせる方向にもっていくのが弁理士の大事な仕事なのです。
その際、審査官が上げてきた拒絶理由を鵜呑みにするのではなく、疑いの目をもって論理の穴を探し、反論して拒絶理由の解消へと持っていくわけです。
あと、弁理士の業務の中に鑑定というものがあります。
例えば、クライアントの製品が他社特許を侵害するかどうかの見解を述べる(侵害鑑定)がありますが、相手の特許の権利範囲の穴をつく能力が求められます。
そんなわけで、弁理士は、相手の言い分を素直に納得するのではなく、「本当にそうかなぁ?」と斜めに見る姿勢を待った、ひねくれ者が向いていると思います。
ただし、あまりにも性格が斜めすぎると、それはそれで苦労することになるのでバランスが大事だと思いますが(笑)
まとめ
というわけで、弁理士に向いている人の性格を5つ挙げてみました。
- ペーパーワーク大好き
- 聞き上手
- 勉強家
- 論理的である
- ひねくれ者?
やはり弁理士がやることを考えると、上の要素のいくつかは当てはまっていないと、なかなかやっていくのが難しいんじゃないかと。
弁理士を目指す方の参考になれば幸いです!
弁理士試験は難しい?
弁理士になるためには、弁理士試験に合格する必要がありますが、これがかなり難しい試験です。
最終合格率が7%前後と、国家資格の中でも相当な難関資格になります。
一方で、弁理士資格があれば、転職や昇進に有利になりますし、独立開業が可能になるなど、価値の高い資格でもあります。
弁理士試験の大まかな内容や難しさについては、「弁理士試験の難易度は激ムズ?!合格率・統計データを徹底解説!」を参考にしてみてください!
過去の弁理士試験の統計データに基づいて、当ブログで独自に分析しており、弁理士試験を知る足がかりになるかと思います。
 弁理士試験の難易度は?理系最高峰を目指せ!
弁理士試験の難易度は?理系最高峰を目指せ!
予備校選びはどうする?
弁理士試験を突破するためには、資格予備校が提供する弁理士講座を受講することが欠かせません。
合格のカギになるのが、自分に合った弁理士講座を選ぶことです。
無料説明会や公開セミナーなどを利用して色んな講師の講義を聞いてみて、自分にとってベストな講師を見つけましょう。
代表的な資格予備校としては、
- LEC(東京リーガルマインド)
 ※弁理士予備校の最大手で1番実績あり。短期合格を狙いたいならここ!
※弁理士予備校の最大手で1番実績あり。短期合格を狙いたいならここ! - 資格スクエア
 ※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い
※オンラインの弁理士講座を提供。受講料がLECのほぼ半額と安い
「弁理士資格の勉強で通信講座が良い理由【通学にはないメリット】」という記事で弁理士の通信講座について書いておりますので、こちらもご参考に!
 弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較
弁理士の通信講座おすすめ【2025年版】全予備校を徹底比較