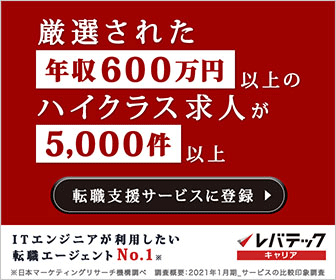大学で理系の学部に進学したのであれば、研究や開発の仕事に就くのが普通です。
しかし、理系の学生や社会人の中には、
自分は研究職に向いてないな・・・
と感じている人もいるのではないでしょうか?
何を隠そう、かくいう私もその一人で、理系の大学院生だったものの、研究職を諦めて文系就職しました(笑)
結果的には、自分に合った仕事が見つけられて良かったと思っています。
というわけで、この記事では、理系だけど研究職に向いていなかった人はどうすればよいか?について書いてみたいと思います!
本記事の内容
なぜ理系なのに研究者に向いていない人がいるのか?
そもそも、なぜ理系なのに研究者に向いていない人が出てくるのでしょうか?
本来であれば、サイエンスに興味があるからこそ理系の学部を専攻しているわけです。
それなのに研究に向いてないと感じるのはおかしな話だと思う人もいるかもしれません。
しかし、理系だけど研究に興味が持てないという人は意外と多いです。(自分も含め)
これには、いくつかのパターンがあって、以下のいずれかに当てはまるのではないかと思います。
- 理系科目が得意だから理系を選んでしまった
- 研究テーマが合っていなかった
- 理系の地味さに嫌気がさした
理系科目が得意だから理系を選んでしまった
数学などの理系科目が得意だった、もしくは、国語や社会が苦手だったので、理系に進んだパターンです。
実は、私も化学や物理の勉強が得意なので、理系を選んだクチでした。
しかし、受験などで理系科目を勉強することと、研究することにはかなり違いがあります。
このギャップのために、「自分は研究は向いていない・・・」と悟る場合が往々にしてあります。
基本的に研究というものは、
課題を発見し、仮設を立てて、実験で検証する
というサイクルをぐるぐる回すもので、受験勉強での頭の使い方(物事を理解する、暗記する)とは異なる部分が多いのです。
また、研究テーマによっては、肉体労働的な作業(測定機器を動かしたり、薬品を運んだり、実験動物を飼育したりなど)の比率が高く、これが原因で研究がしんどくなる、ということもあり得ます。
研究テーマが合っていなかった
本来的には研究に打ち込めるタイプだけど、研究テーマが自分と合っておらず、興味が持てないというパターンもあります。
まず、一口に理系といっても、
数学、化学、物理、生物、機械、電気、情報、医学、薬学・・・
などの大雑把な区分けがあり、その区分けの中に様々な分野が存在します。
例えば、化学を例に取ると、有機化学、無機化学、高分子化学、生物分子化学のように色んなジャンルがあり、さらにその中に無数の研究テーマが存在する、といったかんじです。
なので、数多くの技術分野の中で、自分が本当に興味が持てる研究テーマに巡り合うことは、実は意外と難しいです。
そして、本当に研究分野に興味関心が無いと、研究者としてはなかなか続きません。
理系の地味さに嫌気がさした
就職して、理系の地味さにげんなりする人もいます。
研究者や開発者として企業に就職した場合、研究所や工場などに勤務することになります。
そして、ほとんどの場合、研究所や工場は地方(それも人里離れた山奥)にあります。
例えば、東海道新幹線に乗って車窓を眺めていると、新横浜から名古屋間の辺鄙なところにでっかい研究所がいくつも見えると思います。
研究職に就くとかなりの確率でそういった所で勤務することになります(笑)
そんな地方に住むことになるので、周りに娯楽が少なく、異性との出会いもなくで、仕事が嫌になる人もいるでしょう。
一方で、文系の人は、東京や大阪などの大都市で働いていて、キラキラして見える、というのはありますね。
研究職に向いていないと感じたらどうすればいい?
では、自分が研究職に向いていないと自覚した場合、どうすれば良いのでしょうか?
本当に研究者は続けられないと思ったら、とるべき道は以下の2つしかありません。
- 技術者として異業種に転職を検討する
- 研究者以外の仕事に就く
技術者として異業種に転職を検討する
いきなり研究職を辞めるのではなく、まずは技術者として異業種に転職・就職することを検討するのが個人的には良いと思います。
ここで異業種とは、今の研究テーマに直接関連しそうな業界以外の業界という意味合いです。
上でも述べたように、研究職を辞めたいと思っているのは、「今の研究テーマが自分に合っていない」ことが原因になっている可能性があります。
こういった場合は、研究テーマや職場環境が変わることで、研究へのモチベーションが高まる可能性は十分にあります。
それに、すでに研究職として就職していて一定のキャリアを積んでいるのであれば、これを完全に捨て去ってしまうのは損失が大きいです。
そのため、まずは異業種の技術者として、今までのキャリアを活かしつつも方向転換することは合理的な選択です。
企業の中には、一見その企業とは関係ない分野の研究者を採用することが結構あります。
例えば、
IT企業が新規事業のために、製造メーカーや製薬企業など異業種の研究者を採用する
などの場合ですね。
こういった自分のキャリアが活かせる異業種の求人を効率良く見つけるには、転職エージェントの活用が欠かせません。
特に、後述する研究者の転職に強いエージェントを選択すると良いでしょう。
研究者以外の仕事に就く
中には
やはり研究者は自分に向いておらず、どうしてもそれ以外の仕事をしたい・・・
と考えている人もいるでしょう。
その場合は、研究者以外の仕事を検討するしかありません。
とは言え、大きく職種を変えることになるので、どうしても年齢の壁が出てきます。
動くとすれば、できれば20代、遅くても30代前半くらいまでです。
もし、あなたが学生や第二新卒であれば、年齢的にキャリア転換は十分に可能です。
以下に紹介する仕事を参考に、方向性を考えてみると良いでしょう。
理系の強みが生かせる研究職以外の就職先
では、研究職以外の理系の就職先としてどんなところがあるのでしょうか?
研究者を目指していたのであれば、これまで理系の勉強をがんばって、それなりの専門知識を身に着けてきたと思います。
そのため、就職先を選ぶ際は、理系の強みや知識を活かしたいと思うのが人情でしょう。
理系の強みとして挙げられるのは、
- 理系的な基礎知識(数学、物理、化学など)がある
- 専攻した専門知識(ソフトウェア、機械、バイオなど)がある
- データを元にロジカルに物事を考えることに慣れている
- 数字に強く、分析に長けている
あたりかなと思います。
そんな理系の強みが生かせる研究職外の就職先を挙げていきます!
- 大手企業の知財部、特許事務所
- IT企業(企画など)
- コンサルティングファーム
- 技術営業
- 公務員
大手企業の知財部、特許事務所
まず、理系の強みを活かせる仕事としては、知財の仕事があります。
一番初めに持ってきたのは、私自身が研究者を諦めて新卒で知財の仕事に就いた、という経緯があるからです(笑)
知財の仕事では、主に、研究者や開発者がした発明について特許出願をしたりします。
この仕事には、発明を理解するための理系的なバックグラウンドが不可欠ということで、理系の出身者と非常に親和性があります。
実際、研究者やエンジニアをやっていた人が、キャリアの途中から知財の仕事に転身することも多いですね。
例えば、弁理士資格を取って特許事務所に転職したり、企業の知財部に異動したり、などですね。
弁理士(知財の仕事)に理系が多い理由については、下記の記事で詳しく書いています。
 弁理士は理系出身者が8割なのはなぜ?【大学生の僕が目指した理由】
弁理士は理系出身者が8割なのはなぜ?【大学生の僕が目指した理由】
IT企業(企画など)
IT企業は全般的に理系が活躍しやすい就職先だと思います。
というのも、ITサービスではユーザの行動ログなどの詳細なデータが取れるので、データ解析しながら施策を考えるといった、理系的なアプローチが取られます。
あと、ITサービスを構築するのに、ソフトウェアやネットワークの知識の他に、最先端のテクノロジー(AI, IoT, ブロックチェーンなど)を活用します。
これらの技術をキャッチアップするために理系のバックグラウンドが役に立ちますね。
なので、一般に文系の領域とされる企画職でも理系的な素養があった方が有利ですし、実際、そういった職種でも理系出身の人は多いです。
(もちろん、研究・開発が嫌でなければ、バリバリのエンジニアとして入るのもありですが)
コンサルティングファーム
コンサルティングファームも理系の就職先として挙げられます。
理系のバックグラウンドを持つコンサルタントは意外と多くいます。
私の知り合い(理系)も外資系の戦コンに行っていますね。
コンサルタントの仕事は、
- 大量のデータを分析する
- データ(ファクト)をベースに、論理思考(ロジカルシンキング)を積み重ねて打ち手を検討する
といったことが日常茶飯事に行われるので、理系と相性がいいんですね。
技術営業
技術営業とは、ITシステムや医療器具などの専門性の高い分野についてセールスを行う職業です。
MR(Medical Representatives:病院に医薬品のセールスを行う職業)なんかも技術営業に含まれますね。
これらの製品について、技術的に込み入った内容を顧客に説明する際に、理系の強みを活かせます。
基本的には法人営業(一般消費者ではなく企業に対して営業)がほとんどです。
しかし、技術営業とはいえ、営業であることには変わりなく、一定以上の外向性やコミュニケーション能力が求められる仕事です。
なので、根っからの研究者肌の人には辛いかもしれません・・・。
公務員(技術職)
理系のバックグラウンドを活かして公務員になるという選択肢もあります。
国家公務員や地方公務員では、技術職として理系の出身者を採用しています。
採用は、
土木、建築、機械、電気・電子、化学
などの区分に分けて行われます。
仕事内容は、区分や所属する団体によって様々ですが、例えば、インフラ整備や環境保全などの政策立案や運営に関わります。
まとめ
というわけで、研究者に向いていなかった場合のキャリアについて書いてきました。
まとめると、
- 研究に向いていないと感じる要因には、研究テーマに興味を持ていないことなどが挙げられる
- 研究者を辞めたいと思っても、まずは異業種の技術職を検討してみると良い
- 研究者以外の仕事にジョブチェンジする場合は、30代前半くらいまでがリミット
ということですね。
また、理系の強みを活かせる研究者以外の仕事として、
- 大手企業の知財部、特許事務所
- IT企業(企画など)
- コンサルティングファーム
- 技術営業
- 公務員(技術職)
理系なら研究や開発の仕事に就くもの、という世間的な認識がありますが、研究以外のところで活躍している理系出身者は数多くいます。
固定観念にとらわれずに柔軟に考えると思わぬキャリアが開けるかもしれません。
ご参考になれば幸いです!
専攻外の就活
学生の方の中には、「自分は理系だけど、専攻外で就職したい or 就職せざるを得ない」という人もいるでしょう。
本文でもちらっと書きましたが、私も就活の際に、専攻と全く関係がない業界・職種で就職した経験があります。
理系の僕が専攻外の就職をした体験談は下記の記事で書いているので、ぜひ参考にしてみてください!
 理系の就職先で専攻外はあり?|就活のときの僕の体験談
理系の就職先で専攻外はあり?|就活のときの僕の体験談
理系で高年収が狙える仕事は?
就職や転職の場面で、意識せざるを得ないのが年収です。
年収の高い仕事に就きたい、あわよくば年収1000万円を目指したい、という方も結構いるんじゃないでしょうか?
ちなみに、理系出身者の平均年収は40代で600〜700万円程度と言われます。
従って、理系出身で年収1000万円以上を稼ぐには、年収水準の高い会社や業界を狙うなど、それなりの戦略が必要になります。
理系で年収1000万円稼げる仕事については、下記の記事で詳しく書いています。
 理系研究職で年収1000万円稼ぐには?おすすめ企業を紹介
理系研究職で年収1000万円稼ぐには?おすすめ企業を紹介
理系特化の転職エージェント
本文で述べたように、現職の研究の仕事を辞めたいと思っている方は、
- 技術者として異業種に転職を検討する
- 研究者以外の仕事に就く
のいずれかを目指して転職活動をすることになります。
その際は、自分の理系的なバックグラウンドが活かせる求人を見つけたいところです。
しかし、一般的な転職エージェントの場合、担当者が求職者の技術的な専門性をあまり理解してくれない可能性があります。
その結果、的外れなアドバイスをしたり、適切な求人を紹介されない、というケースもあります。
そのため、転職活動の際には、研究者や技術者の転職に強いエージェントを選びたいところです。
理系特化の転職エージェントには、製造業に強いところやIT系に特化したところなど、いくつか種類があります。
例えば、下記のようなエージェントが挙げられるので、ご自身の専門性に併せて選ぶと良いでしょう。
理系の転職エージェントのおすすめは下記の記事で詳しく書いていますので、併せてご参考に!
 理系向けの転職エージェントおすすめ|研究職特化もあり
理系向けの転職エージェントおすすめ|研究職特化もあり